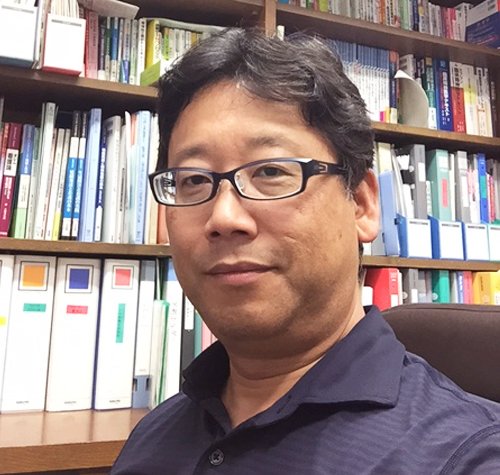新学習指導要領における精神保健教育を実施する高等学校教員に関する研究
- 研究キーワード
- メンタルヘルスリテラシー(MHL) 思春期 学校保健 精神保健 精神疾患

研究シーズの内容
わが国では、MHL教育は精神疾患・障害に関する偏見や差別がネガティブなこととして存在し、なかなか改善できない状況が続いていた。40年ぶりに高校の教科書の改善は精神領域および社会においても非常に大きな変革であり、今後の未来に向けSDGsに準じている点、MHLが浸透する過程に関わる点は、独自性・創造性のある課題と考える。
研究者からのメッセージ
H23年厚労省が重点的に取組む疾患「がん・脳卒中・心臓病・糖尿病」の4大疾病に、「精神疾患」を加え、5大疾患となりました。近年、職場でのうつ病や高齢化に伴う認知症の患者が増加し、予防対策や治療的な対応の必要性が高くなってきています。精神疾患の予防や偏見の改善のためには、精神保健教育が必要であり、小・中学生の時期から正しい知識を得て、継続的に安心して取組める工夫が大切であると思います。
専門分野
精神保健
授業の内容と特長
まずは、看護師課程における基礎的な知識と技術を学ぶわけですが、精神看護学では、セルフケア理論を用いながら、心の病をもった患者さんを理解し、看護過程に沿って展開できるように学びます。また見えない心の表現を可視化できるように講義やコミュニケーション演習を通じて学びます。
研究者になるきっかけは?
精神科看護師として臨床で働く中で、精神医療に対する偏った見方が日本では残念ながら歴史的にも続いていること、様々な精神障がいを持つ当事者や家族の言葉から、学校教育の中で正しい知識と希求行動について学ぶことの必要性があることを知り、MHL啓発するための研究の大切さを感じた。
研究内容を大学での教育や、地域・社会にどのように還元していますか?
精神保健の学習が、2020年から高校生で学ぶことになった現状を踏まえ、看護学生としてより正しい知識と医療の提供ができることを伝えている。またこの研究を、精神障害者家族会の関連団体の要請に応じ、これからの精神保健の変革が始まっていることを講演してきた。
学生や高校生にひとこと!
コスパやタイパばかりを重視する現代社会において、”こころ”ついて学ぶことは、これからの生きていく上で大切だと思いませんか!
大学院で学びたい方にひとこと!
精神看護学分野では、多様化する社会や臨床の中でのメンタルヘルスの問題について深く追究し、精神看護の奥深さや魅力を共に学んでいきましょう!